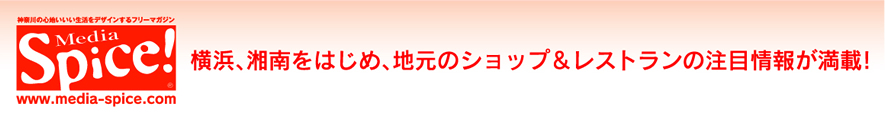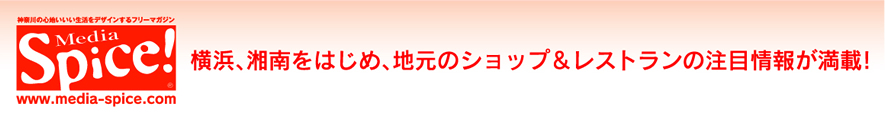�@INDIA��DNA�ɂ̓��e���̓`���ƌ���I�ȃn�C�u���b�h���o���g�ݍ��܂�Ă���B�p�[�J�b�V�����Q�������A��ĉ����ɉ̂��uI Just Want to Hang Around You�v�́A�J�オ��Ɏ˂��z�̂悤�ɂ܂Ԃ����B
�@�u���W���l�قǎ������̉��y�Ɍւ�������Ă��鍑���͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���R�̂ŕ\�����A���ꂪ�Ր��ɐG���JOYCE�̉��y���Ƃ���Ȃ��Ƃ��v���B�uTardes Cariocas�v�͖L���Ȃ�n�[���j�[�̂Â�D��B
�@�����ɂ������āA1���̃X�l�A�����}��3��40�b�͐�̉��B���������ӂ��MARILYN SCOTT�́uLet's Be Friends�v�́A���t���b�V���������Ƃ��̓�����B���O�Œ�������Ɍ��ʂ͑傫���B |
 |
 |
 |
INDIA
�wDICEN QUE SOY�x |
JOYCE
�wTARDES CARIOCAS�x |
MARILYN SCOTT
�wDREAMS OF TOMORROW�x |
|